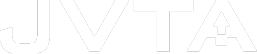明けの明星が輝く空に 第94回 ロボットに支配される世界

【最近の私】山梨県に本谷川渓谷という、紅葉と渓流が楽しめるお気に入りの場所があるのだが、今年はまだ行けていない。もう散ってしまったろうか。
先日まで開催されていた東京モーターショーでは、各メーカーがこぞって、自動運転システムを搭載する車を展示していた。どうやら、ただ車に乗り込むだけで目的地に着く時代が、確実に近づいてきているようだ。
自動運転が実現すれば、便利になることは間違いない。ただ僕は、どうしても漠然とした不安が湧き上がってきてしまう。このまま世の中の自動化が進み、楽なことに慣れ切ってしまった人間は、果たしてどうなるのだろうか、と。
そんな心配は、別に新しいものではないらしい。すでに半世紀前、機械化が進み怠け者になった人間が、ロボットに取って代わられてしまった世界が描かれた特撮作品がある。その作品とは、『ウルトラセブン』(1967~1968年)の第43話「第四惑星の悪夢」だ。
支配者(人間)と被支配者(ロボット)が逆転した構図は、『猿の惑星』(1968年)と共通する。『猿の惑星』の場合、アメリカの公民権運動が作品に影響を与えたと推測される。社会的優位にいた白人が、それまで彼らが差別してきた黒人に取って代わられるかもしれないという恐怖。SFの舞台でその恐怖を映像化し、逆説的に“支配‐被支配”の関係がいかに理不尽であるかを説いたものが『猿の惑星』だ、という解釈も成り立つのではないだろうか。
「第四惑星の悪夢」の場合、『猿の惑星』のように生物同士ではなく、人間と機械の対立にした点が興味深い。当時の日本は、高度経済成長の真っただ中だった。自然が急速に姿を消し、車という機械が幅を利かせて人間は道路の隅に追いやられる。そんな時代だ。劇中、少年が車に轢かれそうになるシーンがあるが、まさにそんな時代に対するアンチテーゼだったのだろう。
ただし、「第四惑星の悪夢」はロボットが人間を支配するようになった原因を、“機械の暴走”とはしなかった。そこが並みのSFとは違うと感じさせる点だが、人類への警鐘が読み取れるセリフとともに、ストーリーを紹介しよう。
主人公のダンと同僚のソガ隊員が、新型の宇宙ロケット「スコーピオン号」のテスト飛行をすることになった。キリヤマ隊長は「スコーピオン号は君たちが操縦するわけじゃない。全て計器がやってのける。(中略)極端に言えば、君たちは終始眠っていていいわけだ」と言って、二人を送り出す。
スコーピオン号は予定航路に乗ったが、予定外の第四惑星に誘導されてしまう。そこは、ロボットに人間が支配される星だった。軍服を着た兵士たち(ロボット)に連行されたダンとソガに、「長官」と呼ばれる男(ロボット)が、その惑星の歴史を語る。「この惑星も昔は、人間が支配していたのだ。わしの記憶装置によると、あれは2000年も前のことだ。人間は我々ロボットを生み出してからというもの、すっかり怠け者になってしまった。(中略)そのうち、ロボットに取って代わられたというわけだ」。
第四惑星のロボットたちは、地球の植民地化を企てていた。二人は危機に陥るも、ダンがセブンに変身し、ロボットたちの野望を打ち砕く。そして、地球に帰還した二人に、キリヤマ隊長が言う。「スコーピオン号のテスト成功を機会に、地球防衛軍は全機関を電子計算機システムに切り替えるつもりだ。みんな楽になるぞ」。その言葉に、ダンは表情を曇らせるしかなかった。
最後のキリヤマ隊長のセリフは、地球も第四惑星と同じ運命をたどるのかもしれないと思わせる。SFに限らず、優れた作品は現実を映す鏡となり、観た者に深い思索を促すが、『第四惑星の悪夢』はまさにそんな作品だ。鬼才、実相寺昭雄監督ならではの映像も味わい深い。昭和特撮を代表する名作であろう。
—————————————————————————————–
Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)
子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている。
—————————————————————————————–
明けの明星が輝く空に
改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る
バックナンバーはこちら